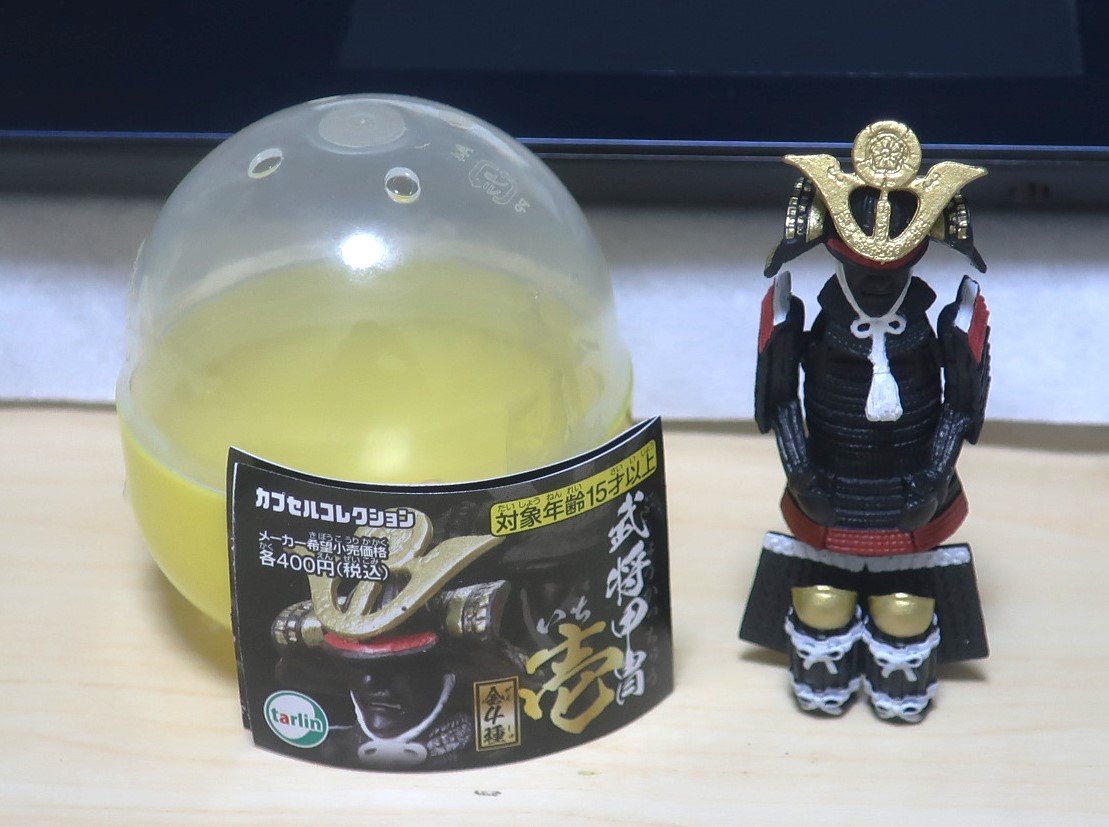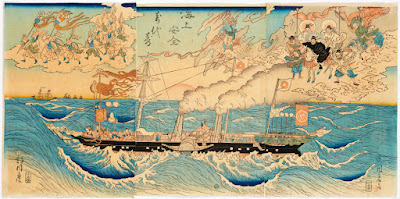東京・南青山の根津美術館では特別展「武家の正統 片桐石州の茶」が開催されています。
 |
| 展覧会チラシ |
今回の特別展は、小堀遠州(1579-1647)や古田織部(1544-1615)のような武将茶人のビッグネームほどは知られていなくても、江戸時代の茶道史上に極めて重要な位置を占めた片桐石州(1605-73)に焦点を当てた展覧会です。
茶の湯の展覧会はこれまで各地の博物館・美術館で開催されていますが、独自の石州流の茶道を開いた片桐石州の名を冠した展覧会は、根津美術館での今回の特別展が初めて。
没後350年を経て顕彰するこの機会に、石州と石州流の茶の湯の魅力をぜひともお楽しみいただきたいです。
それではさっそく展覧会の様子をご紹介したいと思います。
展覧会開催概要
開催期間 2025年2月22日(土)~3月30日(日)
(会期中、前期(2/22-3/9)と後期(3/11-3/30)で一部作品の展示替え、頁替え等
があります。文中、記載のない作品は通期展示です。)
開催時間 午前10時から午後5時(入館は午後4時30分まで)
休館日 毎週月曜日、ただし2月24日(月・振替休)は開館し、翌25日(火)は休館
入館料 オンライン日時指定予約
一般 1500円、学生 1200円
*当日券(一般1600円、学生 1300円)も販売しています。同館受付でお尋ね
ください。
*障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料
展覧会の詳細、オンライン日時指定予約、スライドレクチャー等の情報は同館公式サイトをご覧ください⇒根津美術館
*展示室内及びミュージアムショップは撮影禁止です。掲載した写真は記者内覧会で美術館より特別に許可を得て撮影したものです。
展示構成
1 茶人・片桐石州
2 石州をめぐる人々
3 石州の茶の湯
4 石州の茶の広がり
1 茶人・片桐石州
展示室に入ってすぐにお出迎えしてくれるのは、従五位下石見守に叙任された石州が礼装である束帯を身に着けた姿で描かれた「片桐石州像」。
石州にゆかりの深い大徳寺芳春院の11世・真巌宗乗(1721-1801)が、石州の百回忌のために描かせたものです。
石州は石見守なので「石州」と呼ばれ、大和国(現・奈良県)小泉藩第2代藩主でした。わずか1万3千石の小国ながらも、れっきとした大名だったのです。
 |
| 片桐石州像 洞月筆 真巌宗乗賛 日本・江戸時代 明和4年(1767) 芳春院蔵 前期展示(2/22-3/9) 後期(3/11-3/30)には、「片桐石州像 原在中筆 宙宝宗宇賛 日本・江戸時代 文化9年(1812) 芳春院蔵」が展示されます。 |
石州の茶の湯の師は、戦国武将・桑山重晴の三男・宗仙(1560-1632)で、石州とは江戸屋敷も国許も近かったというご縁もありました。
宗仙は千利休の長男・千道安の弟子で、利休流の侘茶を継承した茶人でした。
2 石州をめぐる人々
石州は、寛永10年(1633)、29歳のとき、徳川家の菩提所、京都・知恩院再建の作事奉行を任じられ、以降、落成までの約8年間、京都に滞在しました。それが、大徳寺芳春院の開祖・玉室宗珀、小堀遠州、千利休の孫・元伯宗旦、大徳寺高林庵・慈光院の開祖・玉舟宗璠といった上方の文化の担い手たちとの交流を行う機会になったのです。
玉室宗珀は石州の参禅の師で、石州は芳春院の隣に片桐家の菩提寺・高林庵を建立し、玉室の法嗣(師から仏法の奥義を伝えられた弟子)・玉舟宗璠を開山に迎えました。
今回の特別展では、石州から高林院に譲られた釜が展示されています(現在は芳春院が所蔵、下の写真中央)。
 |
| 「2 石州をめぐる人々」展示風景 手前が 重要美術品 闘鶏図真形釜 日本・室町~桃山時代 16世紀 芳春院蔵 |
ほかにも石州が国許の小泉の屋敷に遠州風の茶室をしつらえたほど憧れていた大名茶人・小堀遠州に茶入について意見を求めたことがうかがえる遠州の書状も展示されています。
石州が取り上げた茶入について、遠州は、蓋はよく合わせられ、仕覆はことのほか見事な裂である、と誉めているので、石州の喜ぶ姿が目に浮かんでくるようです。
筆者のような素人ではくずし字は読めないので、パネルで原文が表示されているのがうれしいです。
 |
| 書状 片石州宛 小堀遠州筆 日本・江戸時代 17世紀 大和文華館 |
3 石州の茶の湯
今回の特別展の大きな見どころの一つが、現在ではそれぞれ所蔵元が異なる石州愛蔵の3つの瀬戸茶入(※)が揃って展示されていることです。
(※)下の写真右から茶入及びその付属品
尻膨茶入 銘 夜舟 日本・桃山~江戸時代 16~17世紀 根津美術館
肩衝茶入 銘 奈良 日本・江戸時代 17世紀 個人蔵
肩衝茶入 銘 八重垣 日本・江戸時代 17世紀 愛知県美術館(木村定三コレクション)
 |
| 「3 石州の茶の湯」展示風景 |
およそ200回の記録が残されている石州の茶会の中でも注目は、江戸の上屋敷で行われた連会で、道具はほぼ固定して、客組を変えて多数の客を招いて開かれました。
客の中心は、大老、老中を筆頭とした大名から旗本、大徳寺の僧侶など幕府の関係者が多くを占めたのが特徴で、「夜舟」「奈良」「八重垣」は連会でも用いられたため、この3つの茶入は石州の茶会での使用回数の7割を占めていました。
茶道具の展覧会では、茶入だけが単独で展示されるることが多いのですが、石州愛蔵の3つの瀬戸茶入は、茶入を覆う仕覆(しふく)、象牙の牙蓋(げぶた)、内箱、外箱などが並んで展示されているので、仕覆の裂の文様や、牙蓋の形の違いなども楽しむことができます。
ここで注目したいのは、「尻膨茶入 銘 夜舟」の牙蓋。
下の写真、右の牙蓋の下の木型には「小遠」と書かれていますが、これは小堀遠州のことで、武家茶人の大先輩・遠州に対する石州の憧れの強さをここでも見ることができます。
 |
| 「尻膨茶入 銘 夜舟」の付属品 |
石州一世一代の晴れ舞台は、寛文5年(1665)11月8日、江戸城の黒書院で四代将軍徳川家綱に献茶をしたことでした。
その際、道具は将軍家の名物茶道具「柳営御物」の中から選ぶことを許され、これによって石州の評価が定まり、武家茶道における地位を確立したのです。
今回の特別展では、家綱への献茶の時に床の間に掛けられた掛軸と、献茶に用いられた茶入が展示されています。
掛軸の前に畳がしつらえられていて、当時の様子がしのばれます。将軍様を前に石州はどれだけ緊張したことでしょうか。その時の石州の姿を思い浮かべると、手に汗を握って応援したくなる気持ちになりました。
4 石州の茶の広がり
江戸幕府に認められた石州の茶の湯は、幕末に至るまで全国で細かく分派して広まり、石州流は、徳川政権下の「武家の正統」になったと言えます。
ここでは石州流の書や、江戸後期の大名茶人として知られる松平不昧はじめ石州流の茶を学んだ茶人たちゆかりの茶道具などが展示されています。
 |
| 「4 石州の茶の広がり」展示風景 |
井伊直弼が、自身の一派の創立を宣言し、それが名門石州流に連なることを述べている文書も展示されています。
意外と言っては失礼ですが、日米修好通商条約を締結して開国を断行し、筆者にとっては地元・横浜発展の基礎を築いてくれた功労者というイメージが強い井伊直弼が、茶の湯に深く傾倒していたことは初めて知りました。
展示室5 百椿図ー江戸時代の椿園芸ー
毎年恒例となった「百椿図」が今年も展示されています。
江戸初期の椿ブームを背景に制作された「百椿図」が、今回は、公家日記や園芸書にうかがわれる椿園芸の様子や、明治~昭和時代の陶芸家・板谷波山の「彩磁椿文香炉」とともに展示されています。
展示室6 春情の茶の湯
展示室6では、春らしく、草木が芽吹くこの季節にちなんだ華やかな雰囲気の茶の湯の一席が楽しめます。
 |
| 展示室6 展示風景 |
中でもおすすめは、「彫三島茶碗 銘 九重」。
「彫三島」とは、檜垣上の線刻を彫り、そこに白土を施して文様をあらわしたもので、この茶碗のように印花で花文が散らされているタイプは、特に春に好まれています。
花の文様や表面の凹凸をぜひ近くでご覧いただきたいです。
ミュージアムショップ 新商品のご案内
暗がりの中から石州愛用の茶入や、石州自作の茶杓が浮かび上がってくる表紙のデザインがかっこいい特別展図録は、展示作品のカラー図版はもちろん、片桐石州や石州流に関する文献資料などを掲載しているので永久保存版です。
茶会の参加者を、経済学で所得や資産の分配を分析するときに用いられるジニ係数やパレート数で分析する論文は初めて見ました!