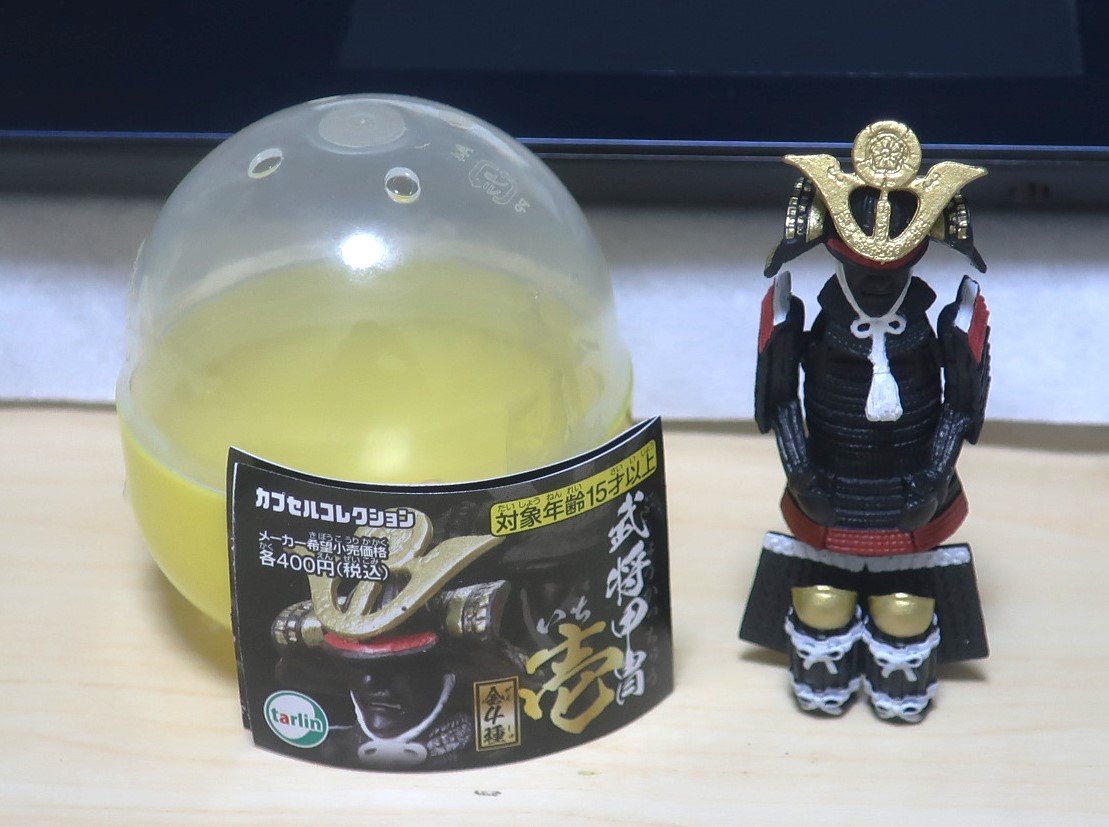東京・虎ノ門の大倉集古館では、企画展「武士の姿・武士の魂」が開催されています。
 |
| 大倉集古館外観 |
今回の展覧会は、平安時代後期以降、歴史の舞台に上り、のちに国を支配するに至った武士たちの戦(いくさ)の様子を描いた合戦図、武士の姿を描いた武人肖像画、武力や権力を象徴する鷹を描いた鷹図はじめ、同館所蔵の名品を中心に武士の姿を描いたさまざまな作品が見られる展覧会です。
そして今回は武士の時代にちなんで、鎌倉時代から江戸時代の同館所蔵の名刀5件も展示されているので、刀剣ファンも見逃すわけにはいきません。
それではさっそく展示の様子をご紹介したいと思います。
展覧会開催概要
会 期 2025年1月28日(火)~3月23日(日)
前期 1月28日(火)~2月24日(月・休)
後期 2月26日(水)~3月23日(日)
開館時間 10:00~17:00 *金曜日は19:00まで開館(入館は閉館の30分前まで)
休館日 毎週月曜日(ただし2月24日(月)は開館)、2月25日(火)
入館料 一般 1,000円、大学生・高校生 800円、中学生以下無料
*展覧会の詳細、ギャラリートーク、各種割引等は同館公式サイトをご覧ください⇒https://www.shukokan.org/
*展示室内は撮影禁止です。掲載した写真は、取材で主催者より許可を得て撮影したものです。
第1章 武者の姿と武具
第1章の大きな見どころのひとつは、なんといっても大倉集古館所属作品の中でも異彩を放つ《洞窟の頼朝》(重要文化財)。今回の企画展のメインビジュアルになっていて、明治時代後期から昭和にかけて活躍した日本画界の巨匠・前田青邨(1885-1977)の代表作ともいえる作品です。
 |
| 左から 重要文化財《洞窟の頼朝》前田青邨 昭和4年(1929) 大倉集古館蔵 《赤絲威大鎧(複製)》平成2(1990)年(原品:平安時代 12世紀) 千葉県立中央博物館 大多喜城分館蔵 《御嶽神社赤威冑》前田青邨 昭和31(1956)年頃 東京国立近代美術館蔵 いずれも通期展示 |
《洞窟の頼朝》は、前田青邨が「十二神将が薬師如来を守護している厳粛な感じ」を描きたいという動機から、源頼朝が平氏打倒を旗印に挙兵したものの、石橋山の戦いに敗れ、洞窟に身を潜めたとされる伝承を思い出して描いたと語る作品で、展示にも工夫が凝らされていています。
並んで展示されているのは、《洞窟の頼朝》で頼朝が着用した鎧のモデルとなった武蔵御嶽神社(青梅市)が所蔵する国宝《赤絲威大鎧》の複製で、一番右は国宝《赤絲威大鎧》の冑(かぶと)を現地で写生した青邨が、昭和32年、限定本『日本の冑』を発行するにあたりスケッチし直した《御嶽神社赤威冑》(東京国立近代美術館蔵)。
甲冑を愛好した青邨が実際に御岳山にのぼり冑を写生をしたくらいですから(筆者も以前現地に行って拝見してきました)、この作品の制作にかけた意気込みが伝わってくるようです。さらに、複製の鎧と《洞窟の頼朝》を同時に見ていると、《洞窟の頼朝》の鎧が立体的に見えてくるから不思議です。
後期には安田靫彦(1884-1978)の重要文化財《黄瀬川陣》(東京国立近代美術館蔵)が展示されて、青邨と靫彦という二人の近代日本画界の巨匠による源頼朝像の競演が見られるので、こちらも楽しみです。
重要文化財や重要美術品の短刀とともに《楠公図》が展示されているのを見つけました。
作者は江戸時代前期の土佐派の画家・土佐光成(1647-1710)。
 |
| 右から 重要美術品《短刀 銘 相州住秋廣/應安三》南北朝時代・応安3年(1370) 重要文化財《短刀 銘 則重》鎌倉時代・14世紀 《楠公図》土佐光成 江戸時代・17-18世紀 いずれも大倉集古館蔵 《修羅道》前田青邨 昭和時代・20世紀 個人蔵 いずれも通期展示 |
楠公とは、鎌倉時代末期~南北朝時代の武将で、後醍醐天皇の鎌倉幕府討伐に応じて挙兵した楠木正成のことで、鎌倉幕府滅亡後、後醍醐天皇による建武の新政に反旗を翻した足利尊氏の軍勢に摂津国(現・兵庫県)湊川で破れ、自刃する運命をたどりました。
この作品では、九州から東上して水陸両方から攻めてくる足利尊氏の大軍に対して、劣勢を覚悟しつつも敢然と立ち向かう正成の姿が描かれています。
明治維新から太平洋戦争の敗戦まで、尊氏は逆臣、楠木正成は忠臣の鑑とされていたことは知っていましたが、君主に忠誠を誓った正成は、江戸時代においても智仁勇を兼備した武将として儒学・兵学において顕彰の対象とされていたことを今回新たに「発見」しました。
自分にとっての新たな「発見」があるのも展覧会の大きな楽しみのひとつですが、今回のもうひとつの「発見」は、小山栄達(1880-1945)でした。
小山栄達は主に官展で歴史画、武者絵を描いて活躍した日本画家で、今回の企画展では、鎌倉幕府軍に包囲された護良親王(大塔宮)が最期を感じ酒宴を催す場面(左隻)、大塔宮を逃がす村上義光の姿を描く場面(右隻)からなる《吉野山合戦》(上の写真)のほか、《源義家雁行乱知伏兵》、昭和11年12月から17年4月まで発行された「子供が良くなる」と謳われた豪華絵本『講談社の絵本』で、日中戦争勃発後に死を賭した英雄や忠臣像を栄達が描いたページが展示されています(下の写真)。
小山栄達の最期もまたすさまじく、太平洋戦争の敗戦が大きなショックとなり、敗戦当日からいっさい口を閉ざし、3日後の昭和20年(1945)8月18日に死去したといわれています。
作品だけでなく、自身も最後まで忠臣を貫いた日本画家だったのです。
第2章 鷹図の世界
第2章では、武力と権力の象徴とされる鷹をクローズアップした作品が展示されています。
 |
| 《鷹図》曽我二直庵 江戸時代・17世紀 12幅のうち 個人蔵 場面替えあり |
この《鷹図》は、もとは屏風絵であったものを掛軸に改装したもので、もとの並び順は不明とのことですが、とても興味深かったのは、1~3歳のオオタカが描き分けられていることでした。
あどけなさを残した1歳から、きりっと引き締まった表情になっていく3歳までの掛軸が並んでいるので、その成長ぶりがよくわかります。
なお、1~2歳までのオオタカは前期のみで、狩りの様子や描かれることが珍しいハヤブサの姿は後期展示ですので、やはり前期後期とも見ないわけにないきません。
また、ここでも新たな「発見」がありました。
曽我二直庵(生没年不明)は、江戸時代の初期に活躍して武家好みの鷹図を得意とした絵師で、曽我派は鷹図流行の立役者だったと考えられていますが、5代将軍徳川綱吉(1646-1709)の生類憐みの令で鷹狩が中止されたことで、鷹図の需要がなくなり没落したと考えられています。
生類憐みの令は、綱吉が戌年生まれだからということで犬だけを大切にした印象がありますが、綱吉の時代には何度となく生類憐みの令が出され、鳥類・魚類・牛馬はじめ広い範囲に対象が広まったので、寛政の改革や享保の改革の時の質素倹約令と同じく、綱吉の動物愛護策まで江戸絵画の世界に大きな影響を及ぼしていたのでした。
鷹狩が復活したのは8代将軍徳川吉宗(1684-1751)の世になってからでした。
復活後の大掛かりな鷹狩は武士の威厳をふたたび誇示しているようにも見えますし、獲物を捕らえた鷹も武士の強さをひときわ強調するように描かれています。こういった作品も時代背景を意識しながらご覧いただくとひと味違って見えてくるかもしれません。
洋風の展示室内のおしゃれな装飾の中、鷹図が続きます。中には笑顔でほほ笑む鷹もいるのでぜひ探してみてください。