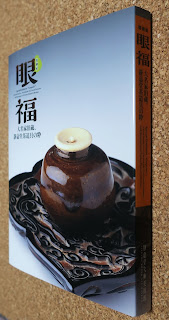京都・相国寺承天閣美術館では、企画展「禅寺の茶の湯」が開催されています。
今回の企画展は、室町幕府第三代将軍・足利義満により夢窓疎石を開山として創建された臨済宗相国寺派大本山の相国寺と、鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)をはじめとした塔頭寺院の協力のもと、国宝1件、重要文化財6件を含む相国寺派寺院の名品全203作品が期間中に展示される超豪華な内容の展覧会です。
(Ⅰ期のみ49作品、Ⅱ期のみ49作品、通期105作品)
実は知っているようで知らなかった禅寺と茶の湯の深いかかわりがわかるとても興味深い展覧会ですので、さっそく展示の様子をご紹介したいと思います。
展覧会開催概要
展覧会名 企画展「禅寺の茶の湯」
会 期 [Ⅰ期]2024年9月14日(土)~2024年11月10日(日)
[Ⅱ期]2024年11月17日(日)~2025年2月2日(日)
休館日 展示替休館 2024年11月11日(月)~11月16日(土)
年末年始休館 2024年12月27日(金)~2025年1月5日(日)
開館時間 10時~17時(入館は16時30分まで)
拝観料 大人800円、シニア(65歳以上)600円、大学生600円、
中学生・高校生300円、小学生200円
※大人の方に限り、20名様以上は団体割引で各700円
※障碍者手帳をお持ちの方と介護者の方一名様は無料
会 場 相国寺承天閣美術館
展覧会の詳細、関連イベント等は同館公式サイトをご覧ください⇒相国寺承天閣美術館
展示構成
第一章 茶の湯の名品
第二章 仏教儀礼と茶の湯
第三章 寛政の茶会 慈照院頤神室
最終章 平成の茶会 鹿苑寺常足亭 落慶披露茶事
※展示室内は撮影禁止です。掲載した写真は記者内覧会で特別に許可を得て撮影したものです。
【第一展示室】
第一章 茶の湯の名品
「茶の湯」というと、茶道具の名品をめぐって争奪戦を繰り広げ、権力の誇示のために茶会を行った戦国武将たちのイメージが強いのですが、実は禅との深いかかわりがありました。
仏教行事の中ではご本尊に茶を供え、書院などで参列者に茶がふるまわれていたのです。
第一展示室の冒頭に展示されているのは、中国や朝鮮から伝来した茶道具の名品です。
 |
| 「第一章 茶の湯の名品」展示風景 |
最初にご紹介するのは、中国から伝来した唐物の茶入《唐物茄子茶入 銘珠光(別名兵庫) 大名物 添利休消息》。
 |
| 《唐物茄子茶入 銘珠光(別名兵庫) 大名物 添利休消息》 一口 中国・元時代 相国寺蔵 Ⅰ期展示 |
さまざまな形をした茶入がありますが、丸い形をしたものは野菜の茄子にたとえて「茄子茶入」と呼ばれています。
ここでは主役の茶入だけでなく、代々作り替えられてきた象牙の蓋や茶入を包む名物裂の仕覆(しふく)、茶入を保存する棗形の木の器・挽家(ひきや)、茶入を入れる黒漆の箱の蓋付などの付属品があわせて展示されているところにも注目したいです。
茶入はさらにいくつもの大きさの違う木箱に入れられているので、この小さな茶入がいかに大切に保存されていたのかがよくわかります。
そして蓋の箱書には千利休以前に選定された「名物」を表す「大名物」の文字が見えます。銘の「珠光」「兵庫」は、この茶入に添えられた利休の文から付けられたものでした。
続いては、黒釉の中にある細かな線条文が、兎の毛並みのようにも、稲の穂先の禾(のぎ)のようにも見える重要美術品《禾目天目茶碗》。
細かい模様をぜひ近くでじっくりご覧いただきたいです。
日本で作られた「和物」の名品も頑張っています。
 |
| 「第一章 茶の湯の名品」展示風景 |
利休の判がすえられている黒漆の天目台「尼ケ崎台」とともに展示されているのは「黄瀬戸珠光天目茶碗」。口縁には真鍮の覆輪がはめられているので、より一層引き締まった感じがします。
(天目茶碗とは鎌倉時代、中国浙江省天目山に留学した禅僧が持ち帰り広めたため、広い口に窄まった高台をもつ形の茶碗を指すことになりました。)
江戸時代初期の茶人で、金森流茶道の開祖・金森宗和の作と伝わり、鹿苑寺境内に建つ「夕佳亭(せっかてい)」を復元した茶室にも名品の数々が展示されいて、茶室の雰囲気をさらに盛り上げています。
 |
| 「第一章 茶の湯の名品」展示風景 |
【第二展示室】
伊藤若冲の水墨画の傑作、重要文化財「鹿苑寺大書院障壁画」の一部を移設した第二展示室に移ります。
第二展示室の展示は、仏教儀式と茶の湯のかかわりがよくわかるのが特徴です。
第二章 仏教儀礼と茶の湯
第二章には、昭和12年(1937)に相国寺第二世・春屋妙葩(しゅんおくみょうは 普明国師)の五五〇年遠忌の法要が相国寺で盛大に行われた際、相国寺本山や塔頭の茶室で設けられた茶席で用いられた春屋妙葩の墨蹟や茶道具が展示されています。
 |
| 「第二章 仏教儀礼と茶の湯ー祖師の遠忌」展示風景 |
相国寺法堂で行われた献茶会には約500名が参列したといわれ、塔頭の茶室でも茶席が設けられ、参拝者たちが訪れたとのことですが、そのときのにぎわいが伝わってくるようです。
 |
| 「第二章 仏教儀礼と茶の湯ー祖師の遠忌」展示風景 |
今回の展示で特に興味深かったのが、京都五山の僧が江戸時代に幕府から朝鮮修文職に任ぜられて対馬に輪番で赴いていたことでした。
将軍の代替わりの際に江戸に赴いた朝鮮通信使はよく知られていますが、約100名ほどの規模の訳官史が江戸時代に57回も対馬を訪れていたことはあまり知られていません。
その訳官史と交流したのが相国寺はじめ京都五山の僧たちだったのです。
当時の文書には、対馬にあった以酊庵(いていあん)で行った訳官史への茶の湯の饗宴の記録などが記録されているので、京都五山の僧たちが外交儀式において重要な役割を担ったことがわかります。
あわせて、約二年の任期で対馬に赴いた僧たちが持ち帰った茶道具も展示されています。
第三章 寛政の茶会 慈照院頤神室
寛政年間(1789-1801)に相国寺の塔頭慈照院の茶室・頤神室(いしんしつ)で行われた茶会の様子が再現されているのが第三章。
 |
| 「第三章 寛政の茶会 慈照院頣神室」展示風景 |
頤神室は、千利休の孫で千家第三世、千宗旦好みの茶室で、茶会の際に狐が宗旦に成りすまして参加したところ、宗旦本人が遅れて登場したので狐はあわてて下地窓を突き破って逃げたというの逸話が残されています。
下の写真左は宗旦に化けた狐が描かれた《宗旦狐図》(慈照院蔵 通期展示)。今でも頤神室の床掛けに用いられている一幅で、今回が初公開です。
 |
| 「第三章 寛政の茶会 慈照院頣神室」展示風景 |
最終章 平成の茶会 鹿苑寺常足亭 落慶披露茶事
最終章には、平成16年(2004)に、鹿苑寺の客殿と常足亭の落慶に際して、表千家不審庵、裏千家今日庵、武者小路千家官休庵、藪内燕庵、遠州茶道宗家、山田宗徧流不審庵の六家元を招いて連会茶事が行われた時の様子が再現されています。
 |
| 「最終章 平成の茶会 鹿苑寺常足亭 落慶披露茶事」展示風景 |
茶事の流れに従って展示が進んで行くので、それぞれの場面でどの什物が用いられたのかがよくわかります。
寄付(よりつき 書院)~客が寄付(よりつき)で身支度を調え、湯を飲み案内を待つ。
本席 初座(ほんせき しょざ 常足亭小間)~茶室に入り、亭主による炭手前が始まる。
懐石(かいせき 客殿)~客は客殿に移し、懐石料理を楽しむ。
本席 後座(ほんせき ござ 常足亭小間)~再び茶室にて濃茶がふるまわれる。
薄茶席 常足亭広間(うすちゃせき 常足亭広間)~小間から広間に移り、薄茶がふるまわれる。
足利義満が造営した山荘、北山殿を母胎とする鹿苑寺で行われたこの茶事は、義満の六〇〇年遠忌事業の一つでもあったので、足利将軍家を意識した什物が随所に登場します。
ただの木の枠のように見える炉縁ですが、実は金閣寺に実際に使われていた木なので、一部にはうっすらと金箔が残っていたりするすごいものなのです。
足利義政が所持していた大名物として珍重された蟹の蓋置。
なぜこれが蓋置?と思ってしまいますが、もとの用途とは違う用途で用いるのは茶道具ではよくあることです。唐物茶入も中国では油壷や薬壺などとして使われていたのです。
この蟹も、もとは義政が庭に置くために制作したものなのです。
本国中国ではあまり知られていなくても、日本では絶大な人気のあった中国禅僧の画家・牧谿が描いた《江天暮雪図》は、画面右下に義満の「道有」品がある東山御物でした。
他にも、唐時代に山中の隠者王休が、来客に川に張った氷を砕いて茶を煎じてもてなしたという故事を描いた円山応挙の《敲氷煮茗図》(通期展示)はじめ数多くの名品が展示されています。
今回の企画展のメインビジュアルになっている国宝《玳玻散花文天目茶碗》はⅡ期の展示です。
重要文化財《唐津鉄斑文水指》もⅡ期展示。
肥前国で窯場で焼かれた陶器のことを唐津焼と呼びますが、鉄釉によって斑文がつくりだされているのでこの名が付いている水指です。