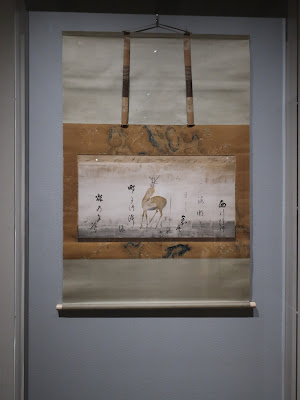東京・上野公園の東京国立博物館では、挂甲の武人 国宝指定50周年 特別展「はにわ」が開催されています。
今回の特別展のキーワードは「50」。
特別展「はにわ」は、東京国立博物館が所蔵する「埴輪 挂甲の武人」が国宝に指定されてから50周年を迎えることを記念して、東北から九州までの約50箇所の所蔵・保管先から約120件の作品が集まり実現した展覧会。そして、これほどの大規模な埴輪展が東京国立博物館で開催されるのは1973年以来、およそ50年ぶり。
さらに国宝「埴輪 挂甲の武人」と同一工房で制作されたと考えられる4体の埴輪が、国内外の所蔵先から集まり、史上初めて5体が一堂に会するという、まさに空前絶後の展覧会なのです。
展覧会開催概要
展覧会名 挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」
会 期 2024年10月16日(水)~12月8日(日)
会 場 東京国立博物館 平成館
開催時間 午前9時30分~午後5時
(注)毎週金・土曜日、11月3日(日・祝)は午後8時まで開館
(注)入館は閉館の30分前まで
休館日 月曜日
(注)ただし、11月4日(月)は開館、11月5日(火)は本展のみ開館
観覧料 本展は事前予約不要です。
一般 2,100円、大学生1,300円、高校生900円
展覧会の詳細、チケット購入方法等は展覧会公式サイトをご覧ください⇒https://haniwa820.exhibit.jp/
展示構成
プロローグ 埴輪の世界
第1章 王の登場
第2章 大王の埴輪
第3章 埴輪の造形
第4章 国宝 挂甲の武人とその仲間
第5章 物語をつたえる埴輪
エピローグ 日本人と埴輪の再会
※展示室内は一部を除き撮影可です。会場で撮影の注意事項をご確認ください。
プロローグ 埴輪の世界
埴輪とは、王の墓である古墳に立て並べられた素焼きの造形のことで、3世紀半ばから6世紀末ごろまで約350年間作られました。
王の墓のために作られたといっても現在の私たちから見ると、決してかしこまったものでなく、ゆるキャラといってもいい愛嬌のある人物や動物たちの埴輪もあります。
今回の展示の冒頭でお出迎えしてくれるのは、まさに東京国立博物館公式キャラクターになっている「トーハクくん」のモデルとなった「埴輪 踊る人々」。
修理完了後の初お披露目です。
 |
| 「埴輪 踊る人々」埼玉県熊谷市 野原古墳出土 古墳時代・6世紀 東京国立博物館 |
「埴輪 踊る人々」との名前がつけられていますが、王のマツリに際して踊る姿とする説のほかに、近年では片手を挙げて馬の手綱を曳く姿との説も有力になっているとのこと。
盆踊りのように手を交互に挙げて踊っているようにも見えますが、後ろに馬の埴輪があることを想像すると確かにそうかもと思えてきました。
第1章 王の登場
まるで古墳の中に入っていくような入口が見えてきました。臨場感あふれる舞台装置がたまらないです。
古墳は王など権力者の墓。副葬品も金銅の装身具や武具、馬具など豪華なものが出土されています。
第1章に展示されているのはすべて国宝。金色に輝く太刀をはじめ古墳時代の国宝がずらりと並ぶ光景は壮観です。
第2章 大王の埴輪
ヤマト王権を統治していた大王の墓に立てられた埴輪は、その大きさに圧倒されます。
下の写真手前は、奈良県桜井市 メスリ山古墳から出土された高さ2m以上もある「円筒埴輪」(重要文化財)。
見上げるほどの高さですが薄さはなんと2cmほどしかないので、技術的にもトップ水準にあったことに驚かされます。
 |
| 「第2章 大王の埴輪」展示風景 |
一つの遺跡から出土された埴輪がまとまって展示されているのもうれしいです。
継体天皇の陵(みささぎ)とされる今城塚古墳から出土された埴輪は、壁面の航空写真のパネルとともに展示されているので、その場にいるような気分になってきます。
 |
| 「第2章 大王の埴輪」展示風景 |
第3章 埴輪の造形
埴輪が出土したエリアは、近畿地方(特に奈良県や大阪府)を中心に、北は岩手県から南は鹿児島県まで、全国各地に広がっています。
第3章には各地域から円筒埴輪や馬型埴輪など個性的な造形の埴輪が大集合しています。
一瞬、「古代メキシコの遺跡か!」と思いましたが、壁面のパネルは築造当時の姿に復元された五色塚古墳(神戸市)。国内でもこんな壮大な景観を見ることができるのです。
 |
| 「第3章 埴輪の造形」展示風景 |
第4章 国宝 挂甲の武人とその仲間
そしていよい、5人のきょうだいが史上初めて勢揃いした「挂甲の武人」の部屋へ。
 |
| 「第4章 国宝 挂甲の武人とその仲間」展示風景 |
国内各地とアメリカから駆けつけてくれた、国宝「挂甲の武人」とよく似たきょうだいたちのプロフィールは次のとおりです。
国宝 埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市飯塚町出土 東京国立博物館
重要文化財 埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市成塚町出土 群馬・(公財)相川考古館
重要文化財 埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市世良田町出土 奈良・天理大学附属天理参考館
埴輪 挂甲の武人 群馬県伊勢崎市安堀町出土 千葉・国立歴史民俗博物館
埴輪 挂甲の武人 群馬県太田市出土 アメリカ、シアトル美術館
いずれも古墳時代・6世紀
挂甲とは鉄製の小さな板を何枚もつなげた甲(よろい)のことで、身に着ける武具や、背中の矢入れなど、細部に違いが見られますが、いずれも群馬県太田市域の窯で焼かれ、出土した古墳は太田市や伊勢崎市に限定されている武人たちで、最高の技術で作られた埴輪です。
それぞれ独立ケースに入って展示されているので、360度どこからでも見ることができます。こちらははるばる太平洋を渡りアメリカの地で日本文化を伝える親善大使としての役割を担っている「埴輪 挂甲の武人」。
国宝「埴輪 挂甲の武人」は、平成29(2017)年から平成31(2019)年に実施された解体修理の際の調査で、白、赤、灰色の3色が全体に塗り分けられていたことがわかりました。
今回は実物大で彩色復元された挂甲の武人も展示されています(下の写真左)。意外にも明るい色あいなので驚きました。
第5章 物語をつたえる埴輪
埴輪といえば1体でなく、いくつもの人物や動物などの埴輪がずらりと並んでいますが、その「埴輪群像」は、「埴輪劇場」とも呼ぶべき何かしらの物語を表現しているとのこと。
ここではまさに「埴輪劇場」を体験することができます。
 |
| 「第5章 物語をつたえる埴輪」展示風景 |
「挂甲の武人」5体揃い踏みと並んで、今回の特別展の見どころの一つは「動物大集合」。
鳥や馬の形をした埴輪など、さまざまな動物たちの埴輪が並んでいます。みなさま一番のお気に入りを探してみてはいかがでしょうか。
エピローグ 日本人と埴輪の再会
古墳時代が終わると埴輪は作られなくなりますが、江戸時代に入ると考古遺物への関心が高まり、現在ではゆるキャラとして冒頭ご紹介した「トーハクくん」はじめ、自治体のキャラクターになるなどすっかり大人気。
平成30(2018)年には埴輪大国・群馬県が群馬県内出土の埴輪の人気投票を行った「群馬 HANI-1 グランプリ」が開催されました。
そこで見事優勝したのが「埴輪 笑う男子」(下の写真右)。
踊る人とか馬子ではないかと考えられていますが、現代人の目から見るとどう見ても「笑う人」。この表情を眺めていると自然と心が和んできます。
上の写真左は、中折れソフト帽をかぶった「フーテンの寅」に風貌が似ていると話題になった「埴輪 帽子をかぶる男子」。なんと東京都葛飾区 柴又八幡神社古墳から出土した埴輪です!