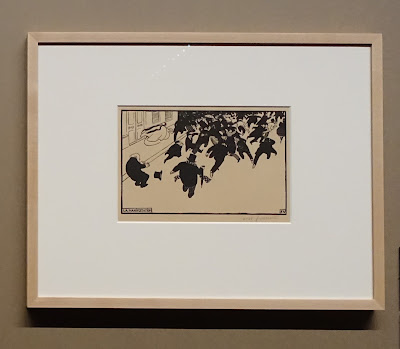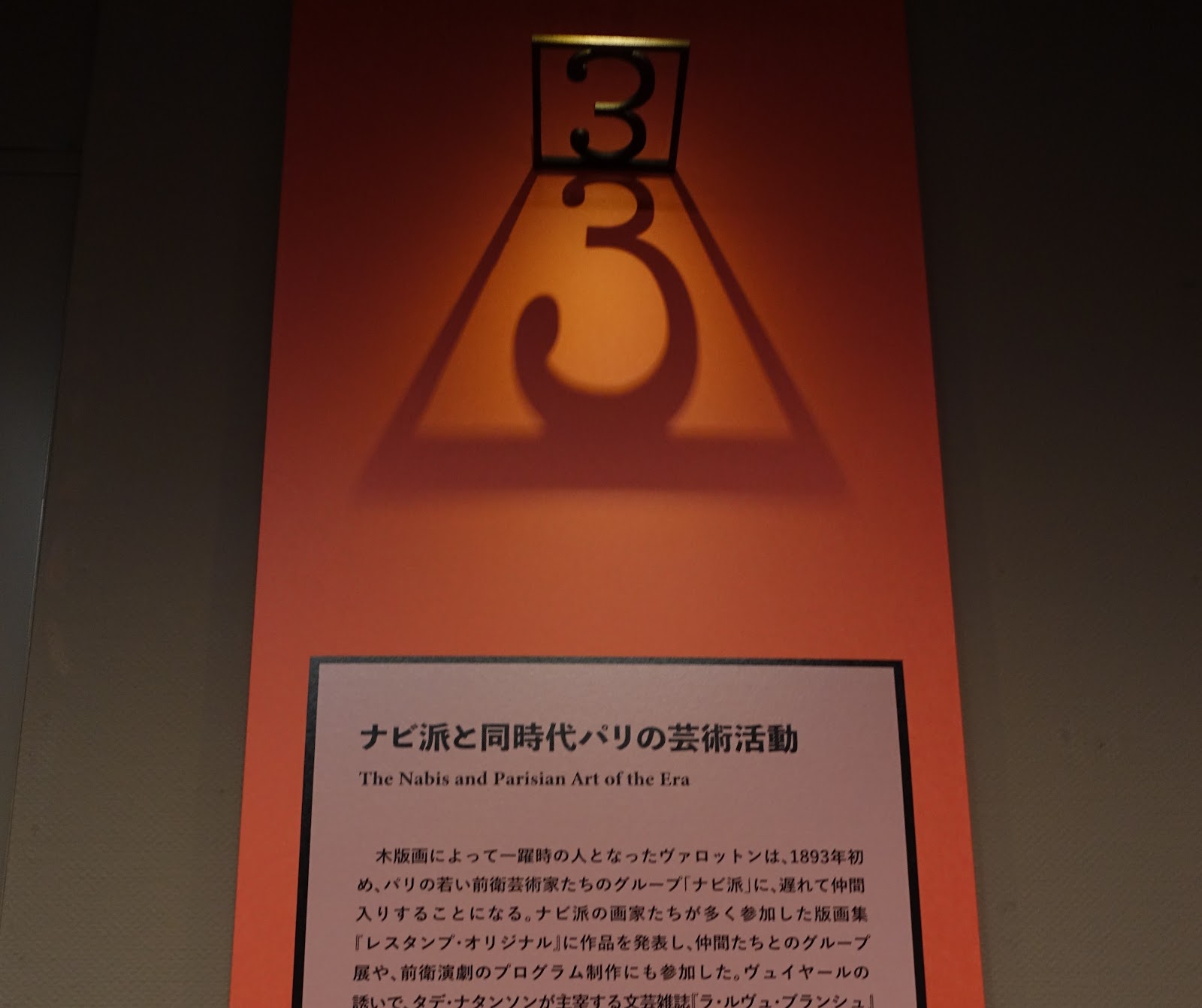東京・日本橋の三井記念美術館では、国宝「雪松図屏風」を中心に、新春を迎えるのにふさわしくおめでたいテーマが描かれた同館所蔵の絵画や工芸作品が展示されている「吉祥づくし」の展覧会が開催されています。
展覧会開催概要
会 期 2022年12月1日(木)~2023年1月28日(土)
開館時間 10:00~17:00(入館は16:30まで)
休館日 月曜日(但し1/9は開館)、年末年始12/26(月)~1/3(火)、1/10(火)
入館料 一般 1,000円、大学・高校生 500円、中学生以下 無料
展覧会の詳細、各種割引等は同館公式サイトをご覧ください⇒三井記念美術館
展示構成
第1章 富貴の華
第2章 長寿と多子
第3章 瑞鳥のすがた
第4章 福神来臨
※展示室内は撮影禁止です。掲載した写真は内覧会で美術館の特別の許可をいただいて撮影したものです。
※展示作品はすべて三井記念美術館蔵です。
美術館ロビーのケース内の作品は撮影可です。
今回は来年の干支、兎が描かれた永樂保全作の《交趾釉兎花唐草文饅頭蒸器》が展示されています。
第1章 富貴の華
オシャレな洋風の内装の中に個別展示ケースが並ぶ展示室1には、大輪の花を見事に咲かせる姿から「花王」「富貴花」など優雅な名前が付く牡丹が描かれた作品が展示されています。
 |
| 展示室1展示風景 |
展示作品も、蒔絵の硯箱、香合、白磁、さらには茶道具を入れる仕覆(しふく)に牡丹の花が刺繍されているものまであって、バラエティに富んでます。
 |
| 展示室1展示風景 |
魔除けの聖獣とされる獅子や、子孫繁栄を象徴する蔓草などともに描かれた名品の中には、今まで「名品展」というくくりでは展示することができなかった珍しい作品も展示されています。
下の写真左の卵の形をした《孔雀卵香合 了々斎好》は、なんと本物の孔雀の卵!
中をのぞき込んでみると、小さいながらも金色に輝く牡丹の花が見えてきます。
 |
| 展示室1展示風景 |
メインの一品が展示される展示室2は、いつも何が展示されるのだろうと楽しみにしているのですが、今回は重要文化財《玳皮盞 鸞天目》が展示されていました。
内側には尾の長い2羽の鳥が優雅に飛んでいる姿が描かれています。
この鳥は鸞(らん)という中国の伝説上の霊鳥で、君主が徳をもって世を治めた時にのみ姿を現すとされている瑞鳥です。
第2章 長寿と多子
国宝の茶室「如庵」を再現した展示室3には、兎が描かれた樂旦入作の《黒楽兎彫文茶碗》が置かれ、床の間には、夫婦愛、長寿の理想を表わす謡曲「高砂」を題材にした(伝)狩野元信筆の《高砂図》が掛けられていて、新春らしくおめでたいしつらえになっています。
展示室4は鶴や亀、松竹梅といったおなじみの題材や、猫やライチといった中国絵画に見られるおめでたい題材の絵画が中心に展示されています。
正面にはお待ちかねの円山応挙筆の国宝《雪松図屏風》が見えてきました。
 |
| 展示室4展示風景 |
堂々とした幹、冬でも変わらない緑の葉から、長寿の象徴の松が画面いっぱいに描かれてる国宝《雪松図屏風》は、今年4月のリニューアルオープン後、初めてのお目見え。
松の幹に積もる雪は上から色を重ねたのでなく、白地を残したものなのですが、なぜか盛り上がっているように見えていましたが、LED照明になって松の輪郭や雪の質感がより一層くっきり見えるようになったので、作品の良さがさらに引き立つように感じられました。
今までとは違う見え方をする国宝《雪松図屏風》をぜひご覧いただきたいです。
江戸中期に来日して日本の絵師たちに大きな影響を与えた中国・清の画家・沈南蘋の作品6点はじめ、中国絵画が多く展示されているのも今回の展覧会の見どころの一つです。
いたずらっぽそうな表情と、しっぽのふわふわ感をじっくりご覧いただきたいです。
沈南蘋の作品が続きます。
ライチは害虫の被害を受けにくいので長寿に通じ、瓜は蔓が延びるので子孫繁栄につながるなど、どの作品にもおめでたいものが描かれているので、解説パネルを読みながら絵の意味を読み解いていくのも楽しいです。
第3章 瑞鳥のすがた
展示室2の鸞(らん)に続いて、展示室5には鶴や鳳凰、末広がりの「八」の字が入っている叭々鳥はじめ縁起のいい鳥が描かれた工芸作品や絵画が展示されています。
夫婦円満の縁起物としてのイメージが付いたキジ、疫病除けの玩具「みみずく達磨」など日本で「縁起物の鳥」とされた鳥の工芸作品や絵画も見られます。
こちらは円山応挙門下の源琦の筆による《東都手遊図》。
中央の「みみずく達磨」は子供を天然痘から守るお守りとして好まれていた玩具でした。
展示室6に展示されているのは、鳳凰、花鳥、七福神の寿老人などおめでたい題材の香合。
小さな香合に乗っている鴨や鹿がとても可愛いです。
 |
| 展示室6展示風景 |
第4章 福神来臨
今も昔も縁起物として親しまれているのは七福神。
展示室7では、七福神の神様たちが描かれた作品がお出迎えしてくれます。
 |
| 展示室7展示風景 |
こちらは七福神、朝日、松竹梅、鶴亀と縁起物が勢揃いした《七福神図》。
作者は江戸時代後期の狩野派の重鎮・狩野養信。
七福神の楽しそうな表情を見ていると、こちらまで気分が和んでくるように感じられました。
 |
| 七福神図 狩野養信筆 江戸時代・19世紀 三井記念美術館 |
七福神の中でも、商家である三井家にとって大黒天、恵比寿の二神は特に重視されていて、商売繁盛を願い年2回行われる恵比寿講では、三井家のご当主が描いた《恵比寿・大黒図》が飾られていました。
今回の展覧会では三井家のご当主たちが描いた七福神の作品が展示されていますが、ご当主たちの見事な腕前に驚かされました。
 |
| 展示室7展示風景 |
ミュージアムショップも新春のいろどり
ミュージアムショップはすっかり迎春ムードに包まれてます。
国宝《雪松図屏風》関連グッズも充実しているので、お帰りにはぜひお立ち寄りください。